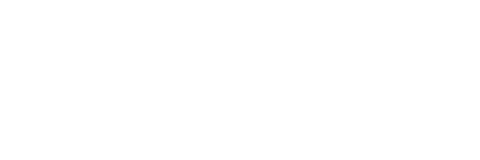HISTORY#EPISODE-01
先進の技術が生み出したカプセル製剤の選択
手探りからのスタート
佐藤薬品工業は、「少品種大量生産」「設備の近代化と経営の合理化」を目標とする製薬業界の流れの中で、カプセル製剤の研究・試作に見通しをつけ、設備機械の充実、増資に次ぐ増資によって、本格的にカプセル製剤一筋の道を進むことになる。
昭和36年(1961)、まったく手探り、手作業でのスタートだった。顆粒をつくり、練り、篩(ふるい)にかけ、乾燥させる。詰めるカプセルは国産のゼラチン製だった。
当時、カプセルの製造は、兵庫県姫路市にあったわずか2カ所。それも家内工業によるもので、薬局の調剤用にごく少量しか製造していなかった。海外では剤型として盛んに用いられていたが、国内では関心が低く、ゼラチンのカプセルに粉末、顆粒の薬品を詰めたものと、ゼラチンゲルのシートで被って成型した2種類が「カプセル剤」とされていた。
一般的には、剤型は長さ2センチ、直径7ミリ程度で、無味無臭、糖衣錠よりも即効性がある。また、ゼラチンは酸素を通さないので酸化しやすい成分を保護する、正確な量が服用できる、など多くの長所を備えていた。
ところが、こうしたカプセル剤の長所がわが国の医薬品業界には広く知られていないこともあって、国内においてはカプセル剤の技術は、まだ確立されていないというのが現状だった。それだけに、これを成功させることは佐藤薬品工業にとって、将来的に大きな飛躍をもたらす魅力的なテーマといえた。

手動の佐藤式充填機を考案
最初に使用した充填機は佐藤が考案したもので、手動式だった。機械に100カプセル分の穴を開け、振動させながら顆粒を詰め込むというもので、カプセルのキャップ部分はひとつひとつ糊付けした。全工程に必要とする人数は14〜15人で、充填機の開発から製品化まで苦心惨憺の末、日産3〜4千個のカプセル剤の製造に成功したのである。しかし、肝心のカプセルの入荷が遅れがちで、入荷するのを待って夜遅くまで作業をするという毎日が続いた。
厚生省からの認可が、翌37年(1962)1月に届いた。製品第1号は、3色顆粒の栄養剤『アスビタン』だった。間もなく、カプセル製剤の先進国であるイタリアのザナシー社に優秀な自動シール機があるという情報を入手した佐藤は、すぐさま行動を起こして、同社のカプセル自動シール機を設置した。
第1号機製品『アスタビン』が大きく寄与
この年、生産が軌道に乗り、量産体制に入った。第1号製品である『アスビタン』は、当時の金額で年間約5,000万円という驚異的な売上を達成し、佐藤薬品工業の発展に大きく寄与した。カプセル剤は、いかにも薬品らしい造形美を持つが、加えて透明カプセルに詰められた赤・青・黄色の3色の球状顆粒は外から一目で分かる。まさに”ミラクルパワーの夢カプセル”というがごとくに、『アスビタン』の商品価値を高めたのである。もちろん、顆粒には被膜をかけ、薬剤同士が混合して変化をきたさない技術を施している。
同業他社はどうかといえば、この頃人気の出てきたアンプル剤に注目し、栄養剤や風邪薬を中心にアンプル剤が市場に広がっていた。アンプル剤は昭和37年(1962)に配置用としても認可され、各社は競うように新製品を発表して派手な販売競争を展開していた。このため市場ではカプセル剤は、アンプル剤に押されていた。ところが昭和40年(1965)に発生したアンプル入りかぜ薬による事故によって、カプセル剤が見直されることになる。各社はアンプル入りかぜ薬の製造中止による損失を補填するため、カプセル剤に目を向けた。
こうした中で佐藤薬品工業は、当初から品質面などで不安定要素の多いアンプル剤には見向きもせず、研究開発をカプセル剤一本に絞って成功させてきたが、アンプル入り風邪薬の事件後に設定された「新配合基準」に準じたカプセル剤をバルクで積極的に提供した。『アスビタン』に続く製品開発も、2色顆粒の風邪薬『アスナミン』や頭痛薬、せき止めなどの承認許可を得て、次々と進んだ。

イタリア製全自動充填機導入で本格生産
昭和39年(1964)にはイタリア・ザナシー社製の全自動カプセル充填機を初めて導入し、本格的な生産体制が整った。同機の生産能力は1日当たり5〜6万カプセルという、全国の医薬品業界でも導入例のない画期的な機種で、佐藤薬品工業ではその後も年次計画で毎年増設していった。
この、第1号機は昭和50年(1975)まで稼働し、佐藤薬品工業発展の礎となった。現も、本社玄関の正面に据え付けられ、会社の歴史を物語る貴重な資料となっている。